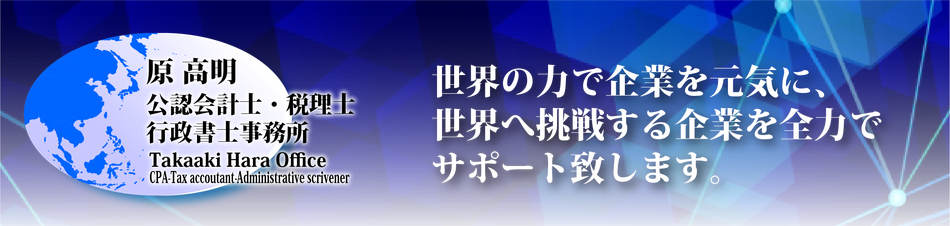〜税制が会計に与える影響 in JAPAN(Part 2)〜
先週、久々にシンガポールに行ってきました。東京など比べても、欧米人、インド系その他様々な顔ぶれの人が入り乱れており、正に国際都市という様相を呈しています。私が最初にシンガポールに行ったのは1990年頃と記憶していますが、その頃はちょっと気を抜くとコレラに感染する国といったイメージを持っており、予防注射をしていった記憶がありますが、現在では非常に整備された、美しい国であります。
シンガポールについては国際物流のアジアの主要なハブである他、税率が安く、キャピタルゲインが非課税(利息や、配当、資産の売却益が非課税)であることから世界中から多くの資金が集まり、富裕層も多く移住して来たことで、一人当たりのGDPが日本を遥かに上回り、限りなく成長を続けているといった印象を有していました。しかしここ最近市内中心部のレンタルオフィスの賃料が2割ほど低下するといったことも起きており、不動産バブルなどにも陰りが出て来たようです。
また最近外国人へのビザの発給が非常に難しくなって来たとの話を聞きました。シンガポール政府としては、シンガポール人の雇用に貢献しないような外国企業については、シンガポールにいくら多額の税金を落とすとしても、社長を含み外国人駐在員に対しビザは出さないといった方向性を強く打ち出して来ている様です。
結局海外から多くの投資を集まったが、長期安定的な発展を目指すためには、安定した雇用を確保することが大切だということに、政府の舵取りの方向が多少シフトしはじめたものと思います。
ただシンガポール人(特に中国系)の評判は“高額の給与のわりに、全く働かない”。ということで、非常に評判が悪く、”出来れば雇用したくない。“という声が多く聞かれます。
日系の銀行や証券会社の現地社員が、日本人の社長よりも給与が高いといったことがざらにあるというようなお話も聞きました。(ちなみに大卒新入社員の方の初任給は28~29万シンガポールドル程度の様です。)。それでは働き方は?というと、日本人の方がはるかに勤勉で、一生懸命働く様です。
また、シンガポールではシンガポルール人が行いたがらない様な業種(いわゆる3K業種)については、特別のビザが用意されており外国人労働者の受け入れが許可されている様ですが、職種の選り好みもかなりある様です。そうなると今後外資系企業としても今までと異なる動きが出てくるかもしれません。
ただ、シンガポールの様に資源が全く無い国の生き方としては、今後も基本的には、従来の方法を推し進めていくしかないと思いますが、今後どのように変化していくか目が離せないような状況にあると思います。
さて前置きが長くなりましたが、前回日本で作成される貸借対照表の多くは、税法の影響を色濃く反映し、世界の中では相当異質なものになっていると書きました。
日本の方法が当たり前と思っていた時に、フィリピンの会計事務所で働き始め、まず固定資産の経理方法について驚いたことを覚えています。
同国の会計基準では、幾ら以上のものを固定資産に計上するのかは会社が任意に決め、法定耐用年数も決まっていません。また減価償却の方法については、定額法が主流でしたが、定率法などその他の方法を採用することも可能です。
いずれにせよ、会社により固定資産の使用方法は異なるし、管理面での重要性も異なるので、ある程度会会社の自由裁量に任せるといった会計慣行がありました。
また税務上も、会計上費用計上した額を、税務上も損金として認めるというものでありましたので、税務上の規定にひきずられること無く、日本に比較し、固定資産の会計上の簿価が、資産の価値をきちんと表しているといった印象を持ちました。
現在世界の多くの国では国際会計基準を採用していますが、そこで一貫して問われているのは、会計上の数値は、企業の価値を正しく示す数値でなければいけないということであると思います。例えば固定資産の耐用年数など定めていませんし、また償却方法についても規定していません。もちろん資産計上の金額基準もありません。そのかわり会社が採用した会計方針について注記を行い、その処理がどのように行われたかを、財務諸表の利用者に対して分かるようにしています。
一方日本では、会計は税務の影響を色濃く受けています。例えば平成28年度4月1日以降に取得する建物付属設備及び構築物の償却方法が定額法のみとなりました。この背景には、「税率は引き下げるが、課税ベースは拡大する。」という政府の考え方が色濃く出ております。赤字法人が約7割である状況を見ると、課税所得を出来るだけ多くするような税制改正の方向性については、今後も続くでしょう。
ただ税法の改正の結果、殆どの会社で、建物付属設備や構築物の償却について、会計上も今までは定率法で処理していたものを、新規取得分からは定額法で償却を実施することになるでしょう。(でも取得する資産の使い方は同じですよね。)
日本の会計はいつまで、このようなことを続けていくのでしょうか。
国際会計基準のように世界統一の会計基準においては、各国の税法規定などが入り込む余地はありません。日本でも世界共通の“ものさし”を導入し、世界中の方に対し自社を積極的にアピール出来る様にする必要があるのではないでしょうか。日本国内だけで生きていくことが難しくなった現在、会計についても世界標準に合わせる必要な時期が来ていると思います。
つい数年前までは発展途上にあると思っていたシンガポールに一人当たりGDPで大きく追い越された現在、真剣に考える必要があると思います。