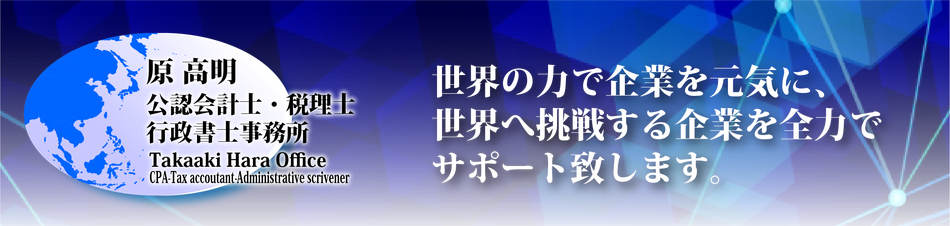前回消費税が10%へと増額された場合に、「インボイス方式」の導入が検討されているということに触れましたが、今回は少し詳しく「インボイス方式」について触れてみたいと
思います。
「インボイス」とは請求書のことですが、EUで使用されている「インボイス方式」の日本語訳において、「インボイス」は「適格請求書」という説明がなされていました。
この日本語を適切な英語で示すと「Official Invoice」といった具合ではないでしょうか。
では「請求書」と「適格請求書」とは何が異なるのでしょうか。
「適格」という意味はいろいろあると思いますが、今回の議論に限って言えば、「消費税率、税額が記載された請求書」ということになります。その上でインボイスに記載された消費税額のみが仕入に関する税額として控除出来ることになります。
現在日本では事業者の消費税の申告のために「請求書等保存方式」が採用されており、帳簿の保存に加えて、取引の相手方が発行した請求書等の客観的な証拠書類の保存を、仕入れに関する消費税額を控除するための要件としています。ただここでは適用税率、税額を記載することは義務図けられていません。
その一方一定の取引について「軽減税率」が適用されるようになれば、取引毎に税率、税額をはっきりさせた請求書が発行されなければ、消費税の処理に関して支障が生ずることになるというのが、「インボイス方式」導入の理由とされています。例えば食品、書籍などは10%への消費税移行時においても8%の税率に据え置くとなれば、複数の税率が混在することになりますので、発行側が「インボイス」に税率、税額を記載してくれれば、税務処理の誤りを軽減することに繋がる事は間違えないでしょう。
ただ検討に上がっているEUスタイルの「インボイス方式」では、免税業者は「インボイス」を発行することが認められておらず、この点がインボイス方式の導入において、大きく懸念される点となっています。
すなわち免税業者がインボイスの発行が出来ないということは、消費税を請求出来ないということになります。
「免税業者については、消費税を納めていないのだから、消費税を付加するのはおかしいだろ!」という話しも聞こえて来そうですが、そう簡単ではありません。
免税業者においても、物品の購入、サービスの提供を受ける際には通常消費税を負担しています。
例えば現在本体価格100円で仕入れたものを200円で販売する例を考えれば、消費税込みでは、108円を支払い、216を受領することになります。免税業者の場合には、その差額が利益となりますので216-108=108円が利益となります。
一方通常の課税事業者であれば、受け取った本体価格部分については200円―100円=100円の利益を得ますが、消費税については受け取った16円から支払った消費税8円を差し引いた8円分を納税することになりますので、この取引からの利益は100円です。
そのため現在免税業者は課税業者に比べると8円分得をしています。
しかし今後「インボイス方式」が導入されると、16円分の消費税を請求出来なくなります。そうなると200円―108円=92円の利益となり、課税事業者に比較して8円分損をすることになってしまいます。
それなら「本体価格208円で売れば構わないだろう?」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
そうすれば計算上は課税業者と同様に100円の利益を得る結果とはなります。
しかしこの商品を購入する側からすれば、課税御者より216円で購入した場合には、 16円の消費税額が控除出来ます。しかし免税業者から購入した場合、税額控除は出来ません。結果的に本体価格の差額の8円分高い買い物をすることになります。
そうなると免税業者は結局本体価格200円で売らなければ、課税業者と対等に戦うことは出来ません。その一方自らの仕入において負担した消費税を控除出来ない分だけ、課税業者に対して不利となってしまいます。
すなわち「インボイス方式」を導入した結果、免税業者の益税が排除されますが、それだけでは済まずに、課税事業者に比較して、仕入税額を控除できない分だけ負担が大きくなります。そうするともはや免税事業者を選択するような事業者は殆どいなくなると思われます。
現にEUなどでは、免税事業者などは殆ど存在しないと伺っております。
ただ日本では売上規模が小規模な事業者に対して、事務処理の簡便性の観点から、免税処理を認めて来た経緯があります。売上規模が少ないような事業者では、通常経理処理に費やすことが出来るマンパワーも十分では無く、また益税の金額も大きな金額にはならないということで、免税業者として認められていた訳です。しかし「インボイス方式」の導入が行われることで、事務負担の軽減という観点で認められていた側面もある免税制度の意義が、完全に失われてしまうと思います。今後どのような対応が行われるか分かりませんが、仮にEUスタイルの「インボイス方式」が導入されれば、日本の消費税法の改正上、非常に大きな改正であり、課税ベースの強化を推し進める方向性での一連の改革に乗っ取った改正と言わざるを得ません。
またそうすると、各取引に関して必ずインボイスを入手する必要が出て来ますので、インボイスの授受に関する事務手続きも増大することは間違え有りません。
ただ「インボイス方式」については、消費税の税額控除の可否についてはインボイスが無ければ控除出来ないとされていますが、ここでは法人税、所得税計算上の費用(損金)と認めるための要件とはされていません。
今後私がいたフィリピンの「オフィシャル・インボイス/オフィシャル・レシート」や、台湾の「統一発票」といったものと同様に、これが無いと税務上費用計上出来ないとなると、更に厄介な問題が生じて来ますので、何とかこれだけは避けていただきたいと思います。
ちなみにフィリピンでは、支払時に銀行振り込みを行うケースは非常に少なく、通常相手方に小切手を発行します。これは相手方に支払う際には、必ず「オフィシャル・レシート」を入手して、支払った経費を税務上の費用(損金)に算入する要件を整えるために、代金の受領者よりオフィシャル・レシートを持参させ、それと引き換えに小切手を渡すという自営手段に他なりません。銀行振り込みでは、代金受領者との接触が無いために、「オフィシャル・レシート/ オフィシャル・インボイス」を入手出来る保証がありません。
このように海外での事例を鑑みると、「インボイス方式」の導入については、なかなか課題も多い様に思います。