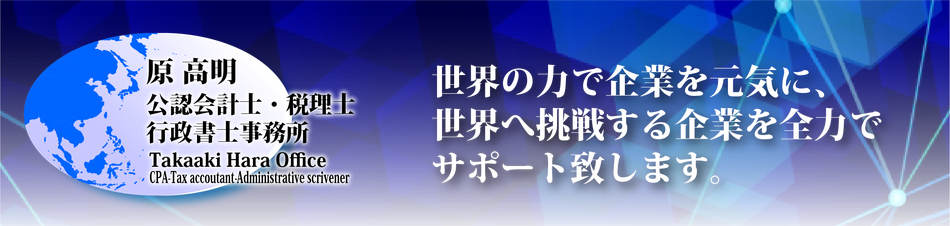「総合課税」と「分離課税」
今年も所得税の確定申告の時期が参りました。確定申告について、サラリーマンの方の多は経験は無いかもしれません。
今回そのような方から、「毎年源泉徴収だけで済んでいたのに、昨年度申告漏れがあったとして、追徴課税処置を受けた。」との話がありました。
その方に詳しくお話を聞くと、勤務する会社の株式について配当があり、配当に関して無申告だとして、ひっかかったというお話でした。
その方の勤務する会社は上場企業では無いため株式は非上場株式でしたが、非上場株式の配当を10万円以上受け取った場合には、確定申告をしなければなりません。10万円未満の場合には、会社より配当を貰う場合に20%の所得税と0.42%の復興特別所得税が差し引かれていますので、その税額を支払うことで、申告は免除されています。しかし非上場株式について、1回の配当で10万円以上を受け取った場合は、この配当については「分離課税」ではなく、「総合課税」の対象となるので、申告が必要だったのですよと説明をしました。
そうすると、そもそも「総合課税」と「分離課税」という意味が分かりませんというお話になりました。
ここで感じたのは、我々が常日頃使用している税務用語について、一般の方はあまり理解されていない場合が多いということです。そこで今回は国際税務を離れ、「総合課税」と「分離課税」について、説明したいと思います。
例えばある方の年間の収入が、給与500万、アパートの賃貸からの純利益が500万、預金利息が500万とします。
実際には給与所得に対しては給与所得控除があり、500万円の場合には346万円が課税対象金額となります。一方アパートの賃貸については、これを事業として青色申告を行えば、65万円の控除が受けられますので、課税所得は445万円とします。青色申告という言葉自体、良く分からないという方もいらっしゃると思いますが、ここでは事業に関しきちんと複式簿記で処理を行い、損益計算書、貸借対照表を作成するといった手間を掛ければ、事業の利益から65万円引いた金額を課税対象の所得としていいという制度と考えて下さい。
実際には社会保険料や、扶養控除、基礎控除、生命保険控除その他の控除があり、課税対象の所得はもっと減りますが、ここでは給与等346万円、賃貸料445万円、利息500万円が課税対象の金額とします。
その際この所得のすべてが総合課税ということになれば、合計1,291万円を課税所得として計算しますので、所得税を計算すると、所得税の金額は2,420,000円となります。また所得税額の2.1%が復興特別所得税として課税されますので、復興特別所得税は50,900円となります。(100円未満切り捨て)。また住民税は課税所得の10%として1,291,000円とします。
しかし実際にはそうはなりません。それは利息については分離課税となっているからです。その意味は、利息については、その他の所得と一緒に計算せず、分けて税金を計算するという意味です。その場合総合課税の対象は,給与等346万円と、賃貸料445万円の合計の791万円であり、課税所得は1,183.000円、復興特別所得税は24,800円となります。(住民税は791,000円)。
一方預金利息に関する税金は、金額の大小に拘らず15%の所得税、5%の住民税及び所得税の2.1%の復興等別所得税の対象となりますので、所得税は75万円、住民税は25万円、復興特別所得税は15,700円となります。
ここで両者の結果を比較します。
すべてが総合課税の場合、所得税2,420,000円、住民税1,291,000円、復興特別所得税50,900円となります。
一方実際には預金利息が分離課税のため、実際には所得税1,933,000円、住民税1,041,000円、復興特別所得税40,500円となります。
そうすると、この方の場合には預金利息が分離課税であることは、所得の全てが総合課税の対象となるより、かなり有利に働いたことになります。
その一方給与所得103万円しか無い方の場合には、所得税、復興特別所得税は全くかからず、住民税は8,000円です。ところが既に退職し給与所得は無いが、預金が沢山あり、103万円を預金利息で稼いだ場合は、所得税は154,500円、住民税は51,500円、復興特別所得税は3,200円かかります。
この場合は給与所得で貰った方が、ずっと特になります。
その理由は皆さんお分かりの通り、累進課税の存在です。所得税率は所得が多くなれば多くなるほど、税率が高くなります。そのため所得が多い方については、累進の税率が、分離対象の所得の税率と比較して高くなれば、分離課税の対象となる所得があった方が有利です。一方所得が低い方の場合には、分離課税の対象となる所得についての税率が、20%などとなると、総合課税の対象として同額を受け取る方が、有利となります。
いずれにせよ「総合課税」は、沢山の種類の所得(具材)を一つの鍋にいれて一緒に税金を計算する方法であり、「分離課税」については、ある所得(具材)だけを他の所得(具材)とは分けて、単独の鍋で税金を計算する課税の方法とご理解いただければ良いと思います。