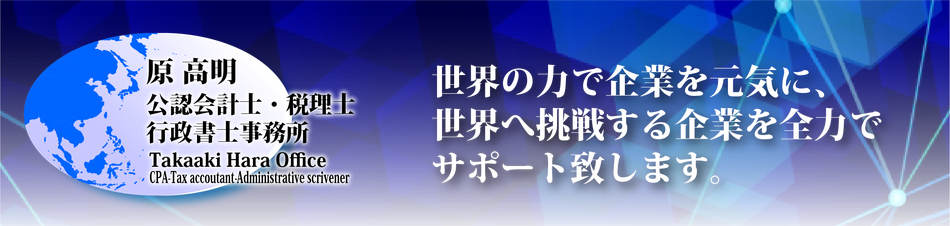今年6月に税理士の先生方向けに行うセミナー資料の準備をしていた際に、経済産業省が平成25年の発行したレポートの「新興国における課税問題の事例と対策」というものが目にとまりました。
その内容を読んでいると、新興国における課税上の問題には、かなり共通する部分があると思い、今回はこのレポートに記載された事例に中から、気になった事例をご紹介し、その内容について検討してみたいと思います。
事例:損金処理の否認
【新興国全般】
ロイヤリティの支払いは利益への対価であるという考え方により、現地子会社が赤字の場合や利益が十分に出ていない場合には、ロイヤリティの支払いに見合うだけの便益を享受していないという理由で、現地子会社が支払ったロイヤリティを損金処理することが否認される場合がある。このようなケースは、中国やインドで、近年多く指摘されている。インドネシアでも、かつては盛んに指摘された。(近年は比較的減少。)
さてロイヤリティは日本語では一般的に使用料と言われていますが、その内容についてはかなり広範囲なものが含まれています。
一般的には財産・権利の使用又は使用の権利の対価として支払われる料金、及びそれらの権利の売却等の処分から生ずる収益とされ、その一般的な内容として特許権、実用新案権、意匠、商標権、ノウハウ、その他知的財産などとされています。
ロイヤリティに関する課税に関し、例えば日中租税条約ではロイヤルティを所有する側の国で課税されるとされていますが、その上でその権利が使用された側の締約国で、10%の源泉徴収を行うことが出来るとされております。そこで中国税務当局は、この支払に関し、当然源泉徴収を要求してきます。
この源泉徴収は、日本企業が中国国内において商標権を使用させ、その対価として収益を受け取ったのですから、中国で儲けさせていただいた所場代として、一定の税金を納めることは理解出来ます。
ただここに記された問題事例に関しては、中国企業が赤字の場合には、この支払はロイヤルティとは認めず、日本企業に対する寄付金であるという理屈で、損金算入性を否定するという話であると思います。
ただ寄付金ということであれば、送金時に源泉徴収を要求することは理屈に合いません。なぜなら日本企業が商標権を提供した対価では無く、中国企業が何ら対価性の無い支払い(=寄付)を行ったと考えるのですから、日本企業が中国国内で行った活動、サービスなどに対する支払いではありませんので、所場代に相当する源泉徴収をされること自体おかしな話です。
それ以上に、実際には日本企業が有する商標などを利用して商売をし、十分な売上が確保できた場合でも、それ以上にコストがかかるようなオペレーションを行っていたとすれば、赤字が発生してもおかしくないわけですから、その赤字の内容について分析もせずに、ロイヤルティの支払いに見合うだけの便益を享受していないと見做し、損金性を否定することは非常に乱暴であると言わざるをえません。
ロイヤルティが高すぎるので、収益を圧迫したということであれば、価格の適正性を問うべき問題であり、これが関連当事者間の場合ならば、移転価格の問題として処理すべき話です。また非関連当事者間の取引であれば、そのロイヤルティの支払について、内容に見合った額として合意の上で取引を行ったのでしょうから、払った側に対し、損金算入性を認めないのは、非常におかしな話です。
最も今回経済産業省が問題としているのは、おそらく中国側の支払者も、日系関連企業が多いためであることは間違いなく、中国における課税リスクを進出企業側に伝える目的で、このような事例を取り上げたのだと思います。
いずれにせよ、中国に進出した場合において、黒字でなければ日本の親会社に対して支払ったロイヤルティが費用として認められないといった話があるとなれば、大きな問題です。
移転価格の場合には、適切な価格を両国間で合意すれば、二重課税の問題は回避されますが、寄付金認定などの場合には、二重課税発生の問題が解決せずに、グループ企業間における取引である場合には、グループにとり大きな負担となってしまいます。
このような乱暴な税務執行が新興国では行われがちでありますが、特に中国においてはこのような話が多い様ですから、留意する必要がありますね。